日本古来の伝統菓子
「おこし」とは米や粟などを熱して干した後、砂糖や水飴に混ぜ型に入れ、乾燥させた干菓子です。 奈良時代には『日本書紀』に穀物を蜜で固めたものが 豊穣祈願で神に奉げられた事が記されています。

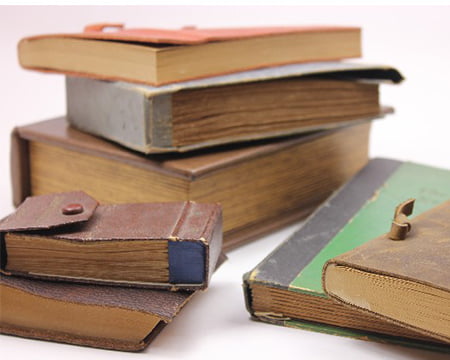
「おこし」とは米や粟などを熱して干した後、砂糖や水飴に混ぜ型に入れ、乾燥させた干菓子です。 奈良時代には『日本書紀』に穀物を蜜で固めたものが 豊穣祈願で神に奉げられた事が記されています。

江戸時代、全国特産品の集散地で“天下の台所”と呼ばれた大坂は「おこし」の原料である良質の米・飴が 手に入りやすい場所でした。 大坂の繁栄と共に「おこし」は<身をおこし・家をおこし・国をおこす>と言われ、大阪名物となり 広く人々に親しまれるようになりました。

「つぶ昆おこし」は「粟おこし」で有名な「あみだ池大黒」と神宗のコラボレーション商品。 昆布を炊いてから乾燥させて粒状にした「つぶ昆」をサクッとしたおこしに合わせました。 メープルシュガーの甘さとつぶ昆の旨味がマッチしたお菓子です。